[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2013年7月号 225号
(2013/06/15)
東日本大震災の原発事故による影響で、日本のエネルギー政策は混迷を極めている。2009年9月の国連気候変動サミットで公約した温室効果ガス25%削減目標は見直さざるを得ず、当初2012年夏にも策定を見込んでいた新エネルギー基本計画は原発の取扱いを巡って議論がまとまらず、その間に政権交代もあり、日本の中長期的なエネルギー政策の指針はいまだ定まっていない。一方、天然資源に恵まれず、製造業を中心とした貿易立国日本にとって、海外からの天然資源の安定調達と国内へのエネルギーの安定供給は、日本の存亡と国際競争力維持には最低必要条件である。しかし、新興国の経済発展によりエネルギー消費量が激増する昨今、自国に存在する資源を自国で管理・開発しようとする資源ナショナリズムも台頭する。限りある希少な天然資源を有する国しか、国家の存続と真の豊かさを勝ち取ることはできないのか。エネルギーを巡る国家や民間企業の動きを見ていきたい。
■ エネルギー開発競争 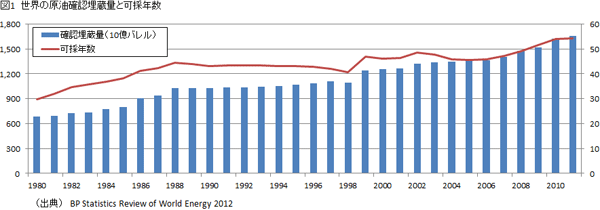
筆者が子供の頃、地球上にある石油資源は約30年で枯渇すると教えられた。1970年代にオイルショックの苦い経験をした日本からすれば、石油やガスなどの天然資源を豊富に有する中東諸国はとても豊かな国に見え、エネルギー資源の輸入量や価格次第で大きく日本経済が翻弄されてしまう状況にあったのも事実である。ところが、図1にあるように、原油は枯渇するどころか確認埋蔵量は年々増え続け、新興国の経済発展による需要増に対応するための生産量の拡大をも吸収している。また、年末の確認埋蔵量を当該年の年間生産量で割った可採年数の増加傾向は、生産量以上に新たな埋蔵量が確認されていることを意味し、「ピークオイル論」は後退しつつある。中東諸国は引き続き有数の天然資源国ではあるものの、現在の原油確認埋蔵量世界一は、新たな油田開発によりベネズエラが取って代わり、カナダもサウジアラビアに次ぐ第3位に上り詰めた。30年前には想定できなかったほど、地球上には海底を含めまだまだ天然資源が眠っており、それらを探し当て、採算性を保ちながらの開発を可能にしたのは技術の進歩である。
『石油の世紀』で1992年のピューリッツァー賞を受賞したダニエル・ヤーギンは、石油の歴史は驚異的なイノベーションの連続であると論じており、現在は「シェール革命」がアメリカを中心に湧き起こっている。頁岩(シェール)層に閉じ込められたガスや油の存在は以前から分かっていたものの、これを破砕して取り出すことはできなかったが、技術革新により効率的かつ低コストの採掘が可能になり、2000年代から本格的な商業生産が始まった。現時点でアメリカの天然ガス生産量はロシアを抜き世界一となり、2012年11月に国際エネルギー機関(IEA)は、2017年にはアメリカが世界最大の産油国になるとの予測を発表、石油の自給自足どころか、輸出も視野に入ってきた。資源開発から生産、流通に多くの雇用が生まれ、特に安価となった天然ガスを主な原料とする石化産業を中心に工場の国内回帰も期待されており、「シェール革命」がアメリカ経済の復権をもたらすとも囁かれている。アメリカが、金融産業に続きエネルギー産業でも世界で先頭に立てるのは、有望な市場に資金と優秀な人材がどんどん集まり、産業の構造転換を促すほどの技術革新を継続して生み出す土壌があるからである。シェール革命に乗り遅れまいと、エネルギー政策の転換を迫られる日本も当該分野での海外進出を進めてきた。
*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]
――4月1日「オリックス・クレジット」から「ドコモ・ファイナンス」に社名変更
[Webインタビュー]