[書評]
2010年12月号 194号
(2010/11/15)
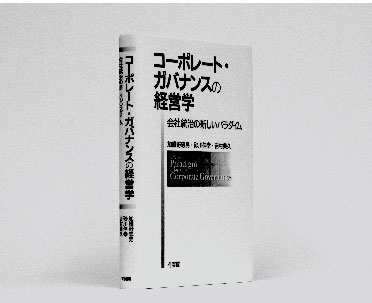 日本企業が弱体化する中、コーポレート・ガバナンスのあり方に関心が高まっている。会社という巨大で複雑な組織が相手なだけに法学、経済学、経営学の3つの学問分野で精力的に研究されている。本書は経営の現場をよく知る3人の経営学者が書き下ろした入門書である。1930年代からの本格的な論議の展開、日本や海外での状況、法学や経済学での考え方、資本コストの視点の大切さ、コーポレート・ガバナンスとコーポレート・ファイナンスの関係などこの問題を考えるうえで必要な基礎知識を平易に解説している。そのうえで、著者らが考える日本の新しいパラダイムとしてあるべきコーポレート・ガバナンスの姿を提示している。
日本企業が弱体化する中、コーポレート・ガバナンスのあり方に関心が高まっている。会社という巨大で複雑な組織が相手なだけに法学、経済学、経営学の3つの学問分野で精力的に研究されている。本書は経営の現場をよく知る3人の経営学者が書き下ろした入門書である。1930年代からの本格的な論議の展開、日本や海外での状況、法学や経済学での考え方、資本コストの視点の大切さ、コーポレート・ガバナンスとコーポレート・ファイナンスの関係などこの問題を考えるうえで必要な基礎知識を平易に解説している。そのうえで、著者らが考える日本の新しいパラダイムとしてあるべきコーポレート・ガバナンスの姿を提示している。
コーポレート・ガバナンスとは何か。著者らは、株式会社がよりよく経営されるようにするための諸活動とその枠組みづくりと定義する。簡単にいえば、誰が経営者を選び、評価し、追い出せるかに関わる制度・慣行である。これを上手く構築できれば会社の健全な発展が促される。コーポレート・ガバナンスの最終目的だ。
この問題は、「所有(株主)と経営(経営者)の分離」がある株式会社特有の問題である。同じ企業でも、両者が一体の個人企業では問題にならない。それで、著者らは、一般に訳語として使われる企業統治でなく、会社統治を使う。会社を預かる経営者が暴走して、会社を破綻させるなどの不祥事は、17世紀の株式会社の発足当時から、何百年にわたり数多く起きてきた。株式会社制度と表裏一体の古い歴史を持つのだ。しかし、学問分野として確立したのは、20世紀から21世紀への変り目の時期に過ぎない。まだ若き学問なのだ。日本では「失われた10年」の時期とも重なり、研究が活発になった。
日本の会社統治の歴史を振り返ると、戦前は株主主権であった。戦時経済期にそれが否定され、戦後は、株主の権利を実質的に制限し、銀行、従業員ら内部のメンバーらが関与する多元的な統治が行われてきた。法の建前では、社長の選任権は株主にあるが、実態は先任の経営者にあり、内部から登用される。その点で経営者を含む従業員主権である。しかし、バブル崩壊と日本経済の長期低迷で、この統治方式に疑問が投げかけられた。90年代以降、米国の株主重視の統治方式への切り替えが叫ばれる。社外取締役制度、内部統制などの仕組みが、会社法、金融商品取引法、証券取引所ルールなどで次々に導入されていく。会社統治の大転換が図られたのだ。
では、その成果は上がったのか。著者らは、上がるどころか、会社組織が上手く機能しなくなり、経営者が短期の業績目標に追われるといった弊害も出ているという。非正規雇用の増大、早まる雇用調整なども、統治改革が間接的にもたらしたものとみる。このままでは日本企業の強みを支えてきた安定した労使関係が損なわれると危惧する。一連の会社統治改革は失敗で、これ以上、繰り返さないために本書の執筆を思い立ったというのである。
著者らは、法学や経済学のように会社統治を株主と会社の視点から議論を始めるのではなく、会社とはいかなる存在かという実態的視点から行うべきだという。会社は、資本と労働など多様な利害関係者が協働する場で、協働を通じて生み出された価値を、協働のパートナーに分配する場だ。価値を生み出すためには経営者がリスクを恐れず、事業投資をしなければならない。会社統治の本質はまさにこの資金使途の意思決定にあるのだが、株主にばかり目がいくと、一番大切な価値の創造に参加している利害関係者への配慮を欠き、多大な悪影響がでる。それは回りまわって株主の利益にもならないという。
法制審議会部会で会社法制の見直しの審議が始まり、企業統治も大きなテーマになっている。本書を読むにつけ、法律学者中心でなく、経済学者や経営学者の意見にも耳を傾け幅広い論議の必要性を痛感する。
(川端久雄)
[M&Aスクランブル]
[Webマール]