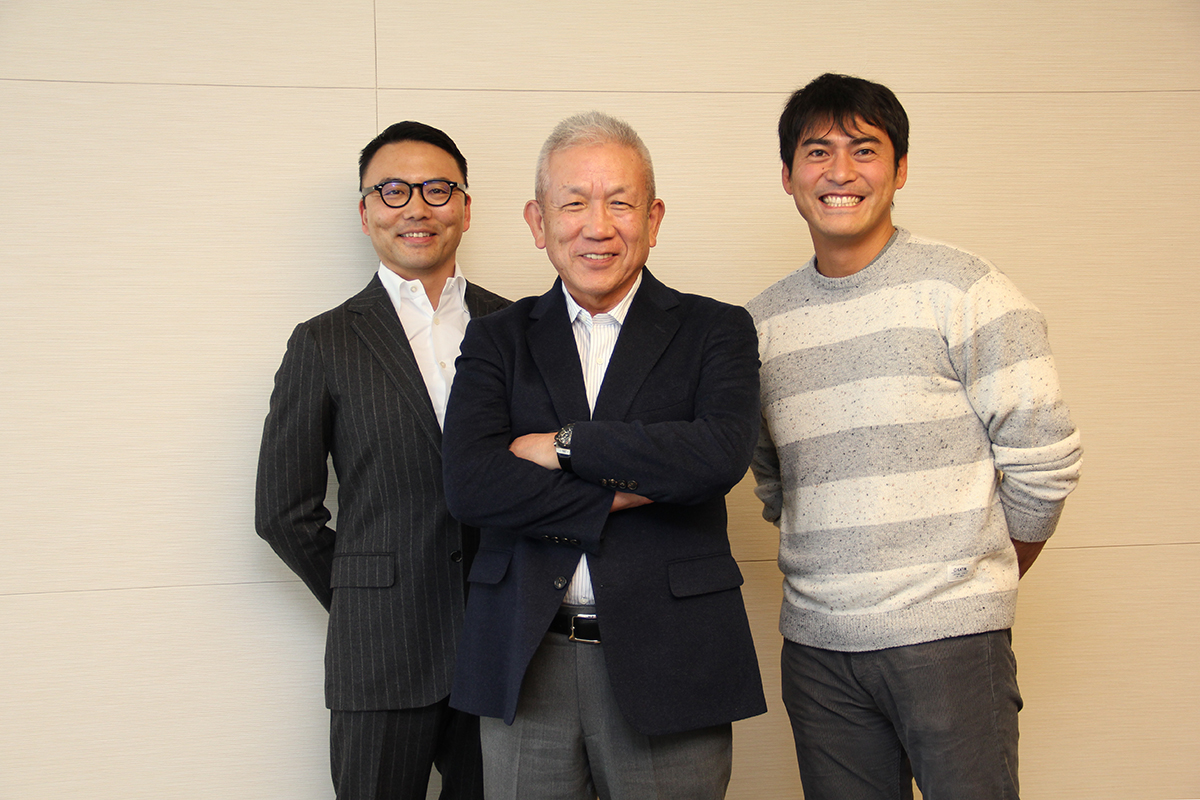原田 泳幸(中央)、加藤 崇(右)久保田 朋彦(左)
自己紹介
久保田 「日本の大企業の代表格のトヨタ自動車が時価総額25兆円、ソニーが9兆円である一方、米国の大企業であるインターネットジャイアント(グーグルやフェイスブック)は、時価総額100兆円です(但し米国でも、オールドカンパニーとして位置づけられたIBMは10兆円規模。この基準でみると、日本の大企業は、全てオールドカンパニーに分類されてしまいます)。
インターネットジャイアントとオールドカンパニーの差は何でしょうか?それは、『成長企業かどうか』である、と私は定義づけています。成長力がなくオールドカンパニーに位置づけられてしまった日本企業が、世界的な競争力を再び獲得し、継続的成長を実現していくためには、これまでの延長線上にはない新しいプロダクトや産業を作り出していくことが求められています。
例えば、ソニーは創業後、トランジスタラジオから始まり、トリニトロン、ウォークマン、半導体(CMOSセンサー)、ベータマックス、VAIO、プレステ等の新しい商品を自ら開発し、世に送り届けることで成長を実現してきました。しかしながら、これは、それぞれ10年ごとのイノベーションサイクルです。デジタル化が進んだ現代においては、1年単位での、新しいイノベーションが求められ、自社開発のみでは、とても世界の成長トレンドには追い付けないことが証明されています。その結果、日本だけではなく、様々なグローバル企業が、自社開発に拘泥するのではなく、社外のリソースを活用して新製品を作り出すチャレンジをしています。
本日は、アップルや日本マクドナルド等のトップを歴任され、この間、エレクトロニクス及び外食産業で、圧倒的な地位を作ってこられた原田泳幸さんと、シャフト(ヒト型ロボットベンチャー)の共同創業者兼取締役CFOを務められ、グーグルに同社を売却後、米国シリコンバレーに活動拠点を移し、フラクタ(水道管の劣化を予測するアルゴリズムの開発)を立ち上げられた加藤崇さんに、日本企業ならではのイノベーションの起こし方について議論していただきたいと考えています。
まず最初に、自己紹介からお願いします」
原田 泳幸(はらだ・えいこう)
1972年日本NCR株式会社入社。研究開発部。90年アップルコンピュータ・ジャパン(当時)入社マーケティング部長。96年米国アップルコンピュータ社バイスプレジデント就任(米国本社勤務)。1997年アップルコンピュータ代表取締役社長兼米国アップルコンピュータ副社長就任。2004年2月日本マクドナルド代表取締役会長兼社長兼CEO就任。05年西友/Walmart社外取締役就任。13年ソニー社外取締役、ベネッセホールディングス社外取締役就任。14年ベネッセホールディングス代表取締役会長兼社長就任。16年6月同社退任。19年12月ゴンチャジャパン代表取締役会長兼社長兼CEO就任、ゴンチャグループグローバルシニアリーダーシップチームメンバー就任。株式会社原田泳幸事務所代表取締役社長。
原田 「私はIT業界33年、最初はLSIもマイクロプロセッサもない時代からキャリアをスタートさせて、急速なIT業界の進化をずっと経験してきました。エンジニア、セールスマーケティング、アップルコンピュータ日本法人の代表取締役社長を務め、その後、日本マクドナルドホールディングスと日本マクドナルドの代表取締役副会長兼CEOとして外食産業11年。さらに、ベネッセホールディングスの代表取締役会長兼社長に就任して、16年6月に退任し、19年12月からアジアを中心に世界で1300店舗超を展開する世界有数のティーブランドであるゴンチャジャパンの代表取締役会長兼社長兼CEOに就任して新たな挑戦をしているところです」
加藤 「私は、11年に東大出身のエンジニアとともに、ヒト型ロボットベンチャーであるシャフトを立ち上げ、共同創業者兼取締役CFO就任し、13年11月に同社をグーグルに売却しました。その後、15年にシリコンバレーに小さなオフィスを借りて、2度目となるロボットベンチャーを立ち上げました。当初は、石油やガス関連のマーケットに点検ロボットを売り込もうと考えて、日本から技術者を呼び、相当な時間とお金を費やしました。しかし、ロボットによるデータ取得には限界があります。AIによるデータ解析のほうが正確で経費も掛からないことことに気がついたことがきっかけで、創業1年半後、ロボットを捨て、AIに特化する、というピボット(事業転換)を決めました。これがフラクタという会社です。道路の下を走っている上水道配管にどの程度余命があるのかを、機械学習・人工知能によって予測し、表示するソフトウェアを開発しています。
加藤 崇(かとう・たかし)
1978年生まれ。早稲田大学理工学部応用物理学科卒業。元スタンフォード大学客員研究員。東京三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)を経て、ヒト型ロボットベンチャーSCHFTの共同創業者(兼取締役CFO)に就任。13年、同社を米国Google本社に売却。15年、人工知能で水道配管の更新投資を最適化するソフトウェア開発会社Fractaを米国シリコンバレーで創業、CEOに就任。著書に『未来を切り拓くための5ステップ』(新潮社)、『無敵の仕事術』(文春新書)、『クレイジーで行こう!』(日経BP)がある。19年2月、日経ビジネス「世界を動かす日本人50」に、同年4月、Newsweek日本版「世界で尊敬される日本人100」に選出。カリフォルニア州メンローパーク在住。『メンローパーク・コーヒー渋谷店』に出資。
一般的に、水道管の平均寿命は100年と言われていますが、米国にあるほぼ全ての水道管の寿命は30年以内に尽きます。米国では日本と比べ破損や漏水事例が多く、老朽化した水道管を新しく更新するためには110兆円もの設備投資が必要と試算されています。しかしながら、どの順番で水道管を取り換えるべきかを予測出来れば、この更新費用の30~40%を削減することが可能です。但し、水道管は地面の下に埋蔵されていますので、地表からは全く判断出来ません。その結果、ランダムに漏水事故は発生します。この問題をどう解決するか。水道管の破損や漏水には、土壌や気象の状態や、配管の年齢など、様々な原因があります。フラクタは、こうした約1000項目の原因を対象とするアルゴリズムによって、水道管のインフラ劣化を予測するソフトウェアを開発し、現在では、サンフランシスコとオークランドの水道会社から始まって、米国22州、55の事業体にフラクタのアルゴリズムを活用していただいています。20年から日本でもサービスを開始する予定です。
ロボットから人工知能に一気にかじを切って、最初のお客さんを獲得できたタイミングで、水処理装置メーカーで世界的に有名な、日本の栗田工業に、過半数の株式50.1%を売却したのが18年5月です。そのトランザクションを17年から久保田さんと一緒にやらせていただきました。株式売却後もCEOとしての私の立ち位置は変わっていません」
イノベーションの要諦は、過去の成功体験を捨てること
久保田 「原田さんは、44年間にわたってグローバル企業に勤めてこられたわけですが、グローバル企業と日本企業の企業文化の差、イノベーションの取り込みへの姿勢の差を感じられることはございますか」
原田 「経営者の考え方の差を目の当たりに経験しましたね。切実に感じたのは、日本人の資質は非常に高いのに、なぜグローバルビジネスでリーダーシップを取れないか、ということです。
私なりに考えてみると、1つ目はステークホルダーマネジメントに必要なコミュニケーション力やリーダーシップが足りないことです。これは言語の問題ではなく文化的な問題です。例えば、新しいビジネスを作ろうとすると、当然リスクが伴います。日本企業の多くは、いかにリスクを排除するか、「×」をもらわないように経営するか、を志向してしまいます。「○」を取りにいけば必ずリスクはありますからね。しかし、ゴルフで言うと、パー狙いでは企業は駄目です。バーディー狙いでいかなければいけない。バーディーを狙えば、時にはトリプルボギーもたたく。そのようなリスクを乗り越えてバーディーを取ることこそが、イノベーションです。日本企業のこういった企業姿勢は、やはり弱い。
サラリーマン経営者、創業者社長に関係なく、海外企業で成功した事例を見ると、トップは強力なリーダーシップを取っています。部下から上がってくる提案を検討するというプロセスを見たことがない。私はアップルで14年間仕事してきて、ジョン・スカリー、マイケル・スピンドラー、ギル・アメリオ、スティーブ・ジョブズ、ティム・クックという5代のCEO全員と仕事をしました。スティーブ・ジョブズとは、7年間一緒に仕事をしました。アップルでは、CEOが代わると、幹部を全員代えます。正しいか正しくないかは別として、全員代えます。そういう意味では、5人のCEOの下でサバイブできた唯一のVP(Vice President)と私は言われました(笑)。人も全部入れ代えるぐらい猛烈なリーダーシップを取って変化をドライブするわけです。そういった経営を見てきて、最近の日本企業の競争力のなさに私は危惧の念を抱いています。まさに今日の議論のテーマである『イノベーションをどうやって実現するか』を一言で言うと、今までの日本企業の成功事例を全部捨てることだと思います」
久保田 朋彦(くぼた・ともひこ)
UBS証券、ソニー、GCAを経て、2014年にデジタル・テクノロジ分野でのインキュベーション事業を手掛けるGCAの子会社アンプリアの代表取締役に就任。15年以上に渡り、メディア、テクノロジ業界にて、日本企業と米国のテクノロジベースの企業とのM&Aや戦略的アライアンスを実現。日米のメディアおよびデジタル・テクノロジ企業をクライアントとしている他、メディアおよびテクノロジ業界でのカンファレンスにも多数スピーカーとして参加。17年7月に日本での体制強化に伴い、GCAテクノベーションに商号変更。
久保田 「イノベーションの要諦は、過去の成功体験を捨てることで、そのためにはトップの意思が非常に大きなポイントになるという原田さんのご意見ですが、一方で、加藤さんは先ごろ、ハーバードビジネスレビュー誌に『ムーンショット経営』に関する寄稿を書かれました。このムーンショット経営の考え方には、日本企業がイノベーションを実現するために、参考になることが多くあるのではないかと思いました。原田さんのコメントを引き継ぐ形で、加藤さんが考えるムーンショット経営とはどういうものか話していただけますか」
ムーンショット経営とは