[M&Aフォーラム賞]
2009年11月号 181号
(2009/10/16)
また、落合誠一・M&Aフォーラム会長(中央大学法科大学院教授、東京大学名誉教授)は、日本のM&Aマーケットの現状とM&Aフォーラムの活動について、
「昨年後半からの、いわゆるサブプライム問題に端を発する金融危機とそれによる実体経済の急激な悪化がグローバルに拡大し大きな問題になっている中で、現在、わが国のM&Aマーケットも一時停滞を余儀なくされております。しかし、持続的な成長を目指すわが国社会にとって、M&Aの機能およびその有効活用は不可欠です。今後も、業界・業種を問わず、新たな事業成長機会の追求や企業価値の向上等を目的に、M&Aは積極的に活用されていくと考えられます。
今回第三回を迎えました『M&Aフォーラム賞』も、賞の趣旨に照らして大いに評価できる作品に恵まれ、正賞、奨励賞、特別賞が決定されたことは、大変喜ばしいことと思っております。
M&Aフォーラムも設立して三年が経過いたしました。徐々にではありますが活動の範囲も拡大しており、実績も積み上げられてきております。皆様には、本フォーラムの活動の趣旨を理解賜り今後ともご支援のほどお願いいたします」と述べた。
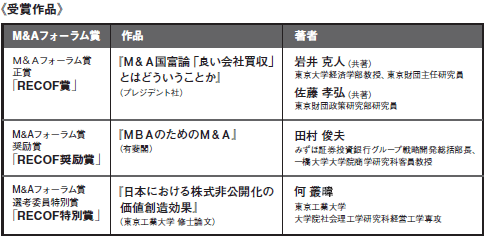

受賞の言葉
岩井克人氏
東京大学経済学部教授
東京財団主任研究員
今回、M&Aフォーラム賞の正賞をいただきました。日頃から尊敬している先生方の審査によって選ばれたことを、大変光栄に思います。また、選ばれたこと自体が嬉しいのは当然ですが、それ以上に嬉しいのは,この本が真の意味で共同作業の産物であり、多くの人と喜びを分かち合えることです。
この本は東京財団における研究会の成果ですが、研究会の中でそれこそ無数の討議を重ねた村松幹二、神林竜、清水剛の三氏、研究会に様々な形で協力していただいた法曹界・経済界・学界の多くの方々、そして実際に本の企画と編集をしていただいたプレジデント社の中嶋愛氏に、深く御礼申し上げます。もちろん、最大の感謝は、ともに本を書いた佐藤孝弘氏に対してです。
佐藤孝弘氏
東京財団政策研究部研究員
この度、「第三回M&Aフォーラム賞正賞」を頂けるということで、大変光栄に思っております。実務的にも理論的にも混乱している会社買収の問題に、具体的な解決策の提言をしたことに高い評価をいただいたものと考えております。本書のテーマである敵対的買収は、昨年秋からの金融危機の影響もあり目立ったケースが少なくなっておりますが、ルールが変わっていない以上、いずれ同種の問題が起こってくると思います。
今後も活発な議論を行うとともに、政策提言を実現するための普及活動を頑張っていきたいと思います。この提言をとりまとめるにあたり、ご協力いただいた皆様にも心より感謝申し上げます。田村俊夫氏
みずほ証券投資銀行グループ戦略開発総括部長、
一橋大学大学院商学研究科客員教授この度はM&Aフォーラム賞奨励賞を頂き、大変光栄です。拙著は、一橋大学大学院商学研究科経営学修士(MBA)コースで担当するみずほ証券寄附講義『M&Aの理論と実務』の講義録です。
実務家として「M&Aは実際にやってみなければわからない」と信じていた私ですが、学生に講義するようになって、「わかったつもり」が本当にはわかっていなかったという体験を繰り返し、理論と実務の双方向からの研究の重要性を痛感しました。本書はそのような実務家が実務家として納得できる理論を求めて悪戦苦闘した軌跡であり、はなはだ荒削りではありますが、今後のわが国におけるM&A理解の進展において他山の石となれば幸いです。
何叢暐(か そうい)氏
東京工業大学大学院
社会理工学研究科 経営工学専攻
この度、M&Aフォーラム賞を受賞したことは、日本に来てから五年目になったばかりの私にとって、予想外の嬉しい結果です。
私は2005年夏、地元の大学を卒業し、親戚のおかげで日本に来ました。最初の二年間はアルバイトで生活費を稼ぎながら、日本語学校に通っておりました。その後、東京工業大学と蜂谷豊彦先生のお蔭で、コーポレートファイナンスの研究を始めました。研究に専念できるとても素晴らしい環境なので、修士論文でも色々と自分のやりたいことができました。蜂谷先生と多くの支えてくれた方々には感謝の気持ちでいっぱいです。この感謝の気持ちを表すには、これからさらに努力し、色々な成果をあげていきたいと考えております。
[Webマール]