[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2013年10月号 228号
(2013/09/15)
3PL、国際化がキーに
国内物流市場は概ねGDPと整合的な動きを見せている。国内物流市場の6割弱を占めるといわれるトラック輸送事業の動きを全日本トラック協会の「トラック輸送産業の現状と課題(平成22年度版)」で見ると、1980年度に5兆266億円だったトラック運送業界の営業収入は90年度には10兆円を超え、バブル期には12兆円に達した。しかし、その後は11兆円台が続き、06年度と07年度には14兆円を超えたものの、リーマン・ショックのあった08年度には13兆円台に減少、さらに09年度には02年度以来の11兆円台へと減少している。ここへきて、安倍新政権による金融・財政政策への期待感が高まり、一部に持ち直しの兆しが見えてきてはいるが、欧州各国の財政不安や新興国経済の減速など不安定な海外経済に対するリスクは払拭されておらず、依然として先行きの不透明感が残っているというのが現状だ。
長年続いたデフレ不況と少子高齢化による消費縮小を背景とした日本の物流市場の減少傾向が続く中で、輸送量の頭打ち、荷主企業からの物流コスト削減要求、同業者間の値下げ競争の激化という3重苦の中にある物流業界についてアナリストが注目しているのが、3PL事業である。
「物流業界の生き残り、成長戦略のキーワードは、『3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)』と『国際化』、そしてその2つのハイブリッド型になっています。荷主企業は景気低迷の中で業種を問わず苦境にあえいでおり、物流コスト削減を狙ったアウトソーシングの流れが続いています。3PLというのは、顧客の荷物の配送・在庫管理などの業務を、プランニングやシステム構築などを含め長期間一括して請け負うアウトソーシングサービスで、SCM(サプライチェーン・マネジメント)の進展による物流の高度化等によって生まれた業態です。物流業者は3 PL業務を遂行する上で自社に不足する機能を補完するため、他事業者との提携などアライアンスを進めており、それは景気の山谷があっても今後とも増えていく事業だと思います」と語るのは、モルガン・スタンレーMUFG証券調査統括本部株式調査部エグゼクティブ ディレクターの尾坂拓也氏。 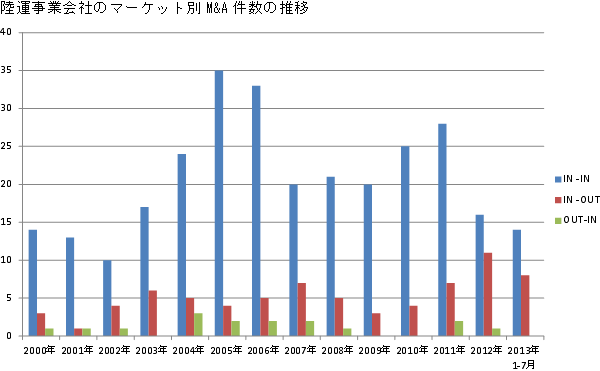
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
- 取得原価配分(PPA)、のれんの償却・減損テストの理解を深める
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]
[Webマール]