[マールインタビュー]
2014年11月号 241号
(2014/10/15)

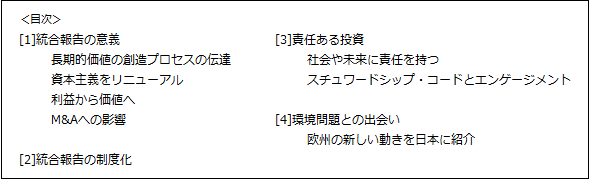
[1]統合報告の意義
長期的価値の創造プロセスの伝達
-- 日本でも統合報告書をつくる企業が増えてきています。どういうものですか。
「日本郵船、オムロン、武田薬品工業、ローソンなどが自主的に意欲的なものをつくっています。元々統合報告は、英国に本拠をおく国際統合報告評議会(IIRC)が提唱した考え方です。IIRCには日本公認会計士協会も加わっています。2013年に国際フレームワークを公表しました。その中で、統合報告書の定義を示しています。それは、『組織の戦略、ガバナンス、パフォーマンス(実績)、将来見通しがどのように組織の短期、中期、長期の価値の創造に繋がるかについての簡潔なコミュニケーション』であるというものです。一言で言うと、企業の長期的な価値創造プロセス(ビジネスモデル)をきちんと投資家に伝達する。投資家の立場から見れば、企業の価値創造能力を正しく評価して投資する。ところが、この価値創造が何を意味するかが、日本ではよく理解されていないように思います」
-- どういうことですか。
「日本で一般的な統合報告の説明は次のようなものです。『まず、財務諸表が企業価値を説明する能力が低下した。つまり財務諸表だけでは、将来キャッシュフローの予測が難しくなってきた。財務諸表の対象にならないインタンジブルな(見えない)資産が企業価値の決定要因として重要になってきたためだ。一方で、CSR(企業の社会的責任)報告書、環境報告書、持続可能性報告書など非財務の情報は増えたが、その中には企業価値と関係のない情報も多く、何が重要かが分かりづらい。そこで、財務情報と非財務情報を統合して、重要な情報だけを簡潔に示す統合報告が必要になったのだ』と。このように企業価値を中心に置く説明が多いのですが、私は違う理解をしています」
-- 先生の理解はどういうものですか。
「今述べた考え方は、投資家に企業価値をよりうまく説明することが必要だ、そうすれば株価が上がる、というものです。こういう議論は、統合報告が提唱される前からありました。これに対して統合報告は、価値を企業価値だけに限定していません。IIRCのフレームワークでは『価値とは組織の活動(企業活動)とそのアウトプットによってもたらされる資本の増加、減少、変換のことである』としています。そしてその資本は株主が提供する財務資本に限らず、製造資本、知的資本、人的資本、自然資本、社会・関係資本の6つの資本が示されています。これらの資本が価値の源泉であり、価値の蓄積でもあります。どの資本でもそれが増えれば価値の創造であり、減ってしまえば価値の毀損になるということです。この場合の価値は、企業自身にとっての価値と社会全体の価値の2種類に分かれます。このように資本と価値の考え方を拡張している点に最大の特徴があります。つまり統合報告が目指しているのは、企業価値を含むより大きな価値の創造についてきちんと報告することなのです」
-- 価値の創造とは何ですか。
「企業価値に限らない価値創造というのはなかなかイメージしにくいかもしれませんが、例えば製薬会社が優れた新製品を開発すれば、それによって会社は利益を得ますから、財務的価値(財務資本)は高まります。同時に、難しい病気が治るようになって、人々の幸せが増進するのも価値の創造でしょう。その技術がさらに次の新薬の開発につながるとしたら、それは知的資本の増加で、それも価値の創造です。また、企業活動が地域で雇用を生み出し、地域住民と良好な関係を築けたらそれも社会・関係資本の増加です。逆に、例えば食品や洗剤の生産にパーム油を使う場合、仮にヤシのプランテーションで森林資源が減少していれば、財務資本は増えたとしても、自然資本が減少し、実は価値の創造に結びついていないかもしれません」
-- これらの資本を計測できるのですか。
「財務資本は計測できますけど、それ以外の資本は数値化したり計測したりできるわけではありません。これはあくまで概念的な話です。大事なのは計測することではなく、こういうものも資本だと認識して、それを戦略や普段の行動に反映させ、外部に説明責任を果たすということです」
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]
[押さえておきたい新時代のM&A~M&Aにおけるデータ&アナリティクス活用]
[マールレポート ~企業ケーススタディ~]