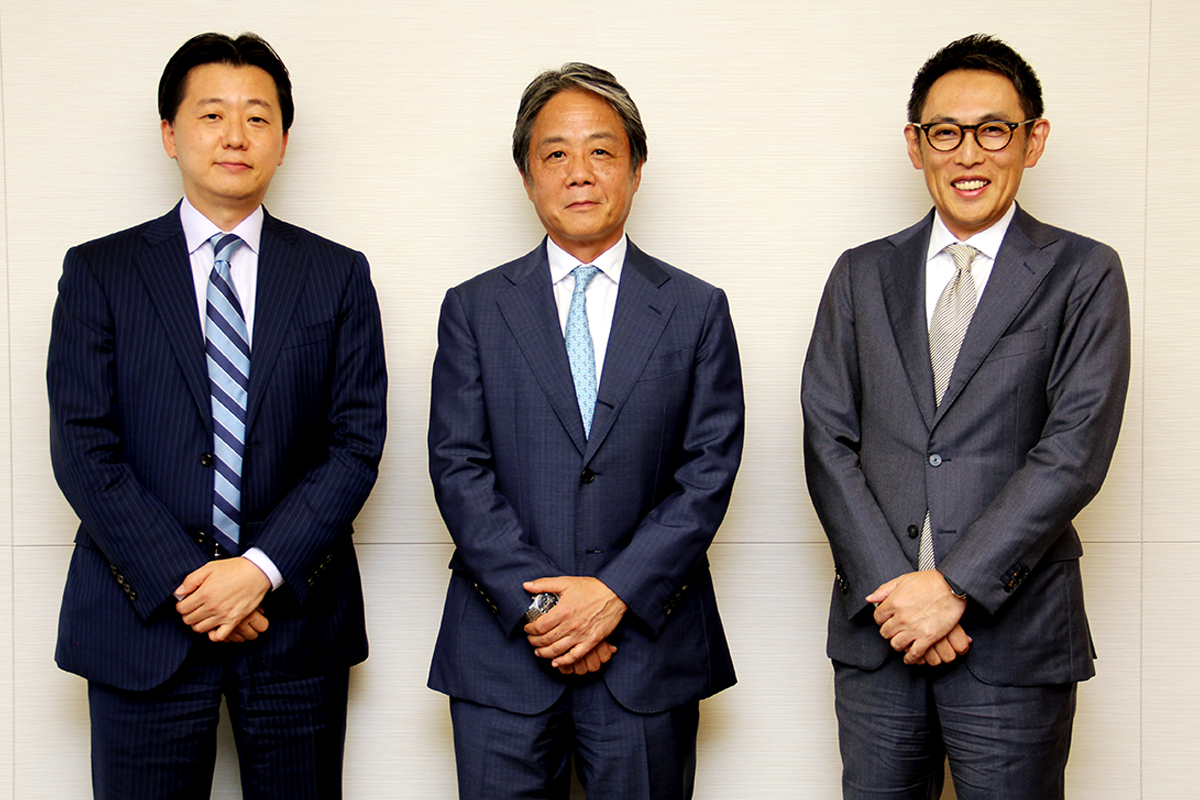左から髙原 達広氏、富岡 隆臣氏、飯沼 良介氏
- <目次>
- 自己紹介
- PEファンドと事業承継を取り巻く環境について
PEファンドに対する創業者、経営陣等の関係者の印象・捉え方
PEファンドにとって投資対象となる事業分野や成長ステージ
創業者・経営陣をめぐる多数の利害関係人との調整のあり方
創業者・経営者への買収スキームの説明とLBOを通じたレバレッジに関する説明について
事業承継案件のデュー・ディリジェンスで重視するポイント - PEファンドによる支援の実際 - 投資後のバリューアップ
半年以内に何をやるかが重要
人材の活用
事業戦略――海外展開の強化がポイント
ガバナンス体制の構築 - PEファンドにとっての事業承継案件のエグジット
- 今後の展望
1. 自己紹介
髙原 「近時、
プライベート・エクイティ(PE)ファンドによる事業承継支援の動きが本格化してきています。本日は、20年以上PEファンド業界で活動されているカーライル・ジャパン・エルエルシーの富岡隆臣マネージング・ディレクターとアント・キャピタル・パートナーズの飯沼良介代表取締役社長にご参加いただき、事業承継案件への取り組みと支援の実際についてご議論していただきます。司会は私、髙原が務めさせていただきます。まず簡単に自己紹介とファンドの取り組みについてご紹介をお願いします」
富岡 「富岡と申します。ゼネラル・エレクトリック(GE)に在籍中の2000年にエクイティ投資に関わって以来、今年で21年間この業界で活動しています。カーライルには2003年に参加しました。カーライル自身も2000年に日本でのオペレーションを開始して、昨年20周年を迎えています。2000年に1号ファンドをスタートし、昨年4号ファンドの運用に入りました。4号ファンドは今までの規模の倍以上の約2600億円となりました。これは、PEファンド業界がこれまでに増して注目され、国内のみならず海外の機関投資家からもかなりの資金が集まる状況になってきているということです。
カーライルは20年間に約28社の投資を実行しています。全てバイアウト投資です。この28社のうち、50%近くが実は事業承継案件です。3号ファンドでは10社投資したうち7社が事業承継案件で、様々な経験談をお話しできるのではないかと思います」
飯沼 「飯沼です。よろしくお願いします。私も2001年にアント・キャピタル・パートナーズに入ってちょうど20年、この業界を経験させていただいています。アント自身も2000年にスタートして20周年を迎えました。私どもはちょうど5号ファンドが終わったところで、今6号ファンドをレイズしています。やはり我々の中でも最大サイズで、過去最高の500億円の規模です。これまでのファンドの規模は小さかったため、そういう意味では回転が速いところもあります。5号ファンドまでで40件強の投資をしていて、我々は6割強が事業承継の案件です。5号ファンドでは10件投資をし、うち6件が事業承継の案件だったと思います。今日は我々の知らない世界である大型の事業承継の取り組みについて富岡さんから話を聞けることを実は非常に楽しみにしています」
髙原 達広(たかはら・たつひろ)
1996年4月に第二東京弁護士会登録。TMI総合法律事務所での執務を開始し、1998年Georgetown University Law Center(LLM)を卒業。Simpson Thacher & Bartlett法律事務所(ニューヨーク)、Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所(パロアルト)での執務を経て、2001年TMI総合法律事務所に復帰し、2003年にパートナーに就任。中央大学法科大学院客員教授(現任)。事業会社やPEファンドによるM&A案件に関与するとともに、上場企業の支配権争いへの対応、未公開企業の事業承継支援、上場を目指すベンチャー企業の支援等、コーポレート分野の実務を幅広く扱う。
髙原 「弁護士の髙原です。1996年にTMI総合法律事務所に入所し、M&A実務に関与しております。1997年夏にアメリカに渡り、留学や現地法律事務所での執務を経験しましたが、その際、PEファンドがアメリカの社会において果たしている役割の大きさを知ることとなりました。2001年に帰国して以来、PEファンドの皆様やPEファンドに事業を売却する皆様をご支援する機会をいただき、現在も、事業承継案件やカーブアウト案件など、PEファンドによる各種投資の現場にリーガルの立場から関与しています。これまで、20年程の間に、事業承継やカーブアウトニーズを捉えたPEファンドによる投資が、様々な産業分野、そして、日本国内の様々な地域で着実に浸透してきたと感じています。私自身、PEファンドの皆様をご支援する中で、日本でのPEファンドの成長とその浸透を実感させていただくことのできた20年でした。本日は、これまで20年余りにわたり、日本のPEファンドによる投資の現場に深く関与されてきたお二方のお話を伺えることを楽しみにしています」
2. PEファンドと事業承継を取り巻く環境について
PEファンドに対する創業者、経営陣等の関係者の印象・捉え方
髙原 「先ほどのお話ではかなりの割合でPEファンドによる事業承継支援が行われているということですが、事業承継というと創業者や経営陣の方はどちらかというと保守的で、ファンドに対してアレルギーを示していた時代があったと思います。最近の変化をどのように感じていらっしゃいますか」
富岡 隆臣(とみおか・たかおみ)
日本長期信用銀行に13年勤務。1998年にGE International, Inc.に移籍。GE Equityの日本代表として、4社を上場させた。
2003年にカーライルに参画して以来、ヘルスケア及びコンシューマー業界の責任者として、クオリカプス株式会社、株式会社ソラスト、株式会社おやつカンパニー、三生医薬株式会社、及びオリオンビール株式会社への投資を主導し、各社の非常勤取締役として企業価値向上に貢献。現在、事業承継投資の責任者として株式会社リガクへの投資を主導している。早稲田大学法学部卒/米ニューヨーク大学にてMBA取得。
富岡 「もう、隔世の感がありますね。それこそ20年間PEに関わってきて、初めのころは経営陣にお会いいただくことは非常に敷居の高いものでした。歴史的にいえば、日本で投資ファンドが認識され始めたのが米リップルウッド・ホールディングスによる日本長期信用銀行の買収に代表される再生型のファンドだったということもあり、『ハゲタカ』などマイナスなイメージが先行し、いわゆる王道のPEファンドの投資に対して理解をしてもらうことが大変でしたが、最近ではむしろ先方から相談に来られるところまで理解が深まっています。それは我々の力だけではもちろんなくて、10年ぐらい前からメガバンク3行をはじめとした銀行や証券会社がPEファンドの担当部署を置くようになってから変わってきたと思っています。特に、大手の金融機関がソーシング活動を支援してくれることで徐々に市民権を得たのではないかと思います。これは必ずしも日本に限った話ではなく、アメリカもヨーロッパも同様の変遷を経てここまで来ています」
飯沼 「全く同感です。いまだに記憶に残っているのは、2002年、私の最初のディールで、愛知県の会社のオーナーと最初に会ったときの第一声が『おたくはハゲタカですか』だったことです。その時代からするとほんとうに隔世の感があります。今では、事業承継を考えているオーナーの方々でファンドをハゲタカと思っている人はほぼいないのではないでしょうか。インターネットや本でこれまでのファンドの実績はしっかり調べていますし、さらには、事業承継するにあたり譲渡先は事業会社とファンドのどちらがいいか。いったんファンドで引き継いでもらって、人材育成を含めてバリューアップできないかといったことまで深く考えている方々が増えてきていますので、そういう意味ではファンドという選択肢が当たり前のようにあると思います」
PEファンドにとって投資対象となる事業分野や成長ステージ
髙原 「皆さまのところに相談がくる事業承継案件は比較的規模が大きな会社や社歴の長い会社が多いと思いますが、PEファンドとして検討対象になる事業分野や成長ステージをどのように捉えていますか」
飯沼 良介(いいぬま・りょうすけ)
1994年三菱商事入社。技術部、コンピュータ事業部にて海外有望ソフトウェアベンダーの開拓と国内事業立ち上げを担当。「ECビジネス・キーパーソンズ」(東洋経済新報社)で紹介されるなどIT業界で広く活躍。2001年当社入社以降、15件の投資に直接関与。投資先においては経営管理体制整備と営業戦略構築面でのサポートを行っている。2012年当社取締役就任。2013年当社代表取締役就任。2019年一般社団法人日本プライベート・エクイティ協会監事就任。慶應義塾大学商学部卒。
飯沼 「ステージはさまざまで、グロースのステージもあれば、成熟したステージもあります。業績が伸びきっているとオーナーが思い込んでいる案件でも、利益面での非効率な部分を変えるだけで
EBITDAが1.5倍とか2倍に変わっていきます。特にアントが対象とする中堅企業ですと、ほとんどがグローバル展開できていないため、例えばグローバル展開をお手伝いするだけでも成長を作ることができる伸びしろがあり、従業員の待遇面を改善してもなお業績が伸びると見ています。そういう意味では、中堅企業の場合、どのステージにおいてもやれることはかなりあると思います」
髙原 「富岡さんはいかがですか」