[書評]
2012年10月号 216号
(2012/09/15)
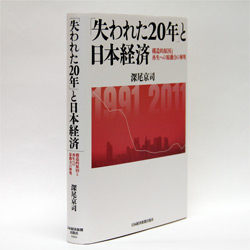 バブル崩壊から既に20年余り。先進国に類を見ない日本の長期経済停滞は「失われた10年」から「失われた20年」と呼ばれるようになった。著者はマクロ経済分析とミクロのデータ分析を組み合わせながらその原因の解明と停滞脱出の処方箋を提示している。
バブル崩壊から既に20年余り。先進国に類を見ない日本の長期経済停滞は「失われた10年」から「失われた20年」と呼ばれるようになった。著者はマクロ経済分析とミクロのデータ分析を組み合わせながらその原因の解明と停滞脱出の処方箋を提示している。
長期停滞の根本に日本経済全体の生産性が上昇していないことがある。著者は、主に生産の効率性や技術水準を測る指標(全要素生産性=TFP)を使って分析していく。
先進国では、産業構造の変化により生産性上昇率の高い製造業が縮小し、低い非製造業が拡大することで、マクロ経済の生産性上昇が減速するといわれるが、日本の減速は、これでは説明できない。生産性の停滞は産業構造の変化でなく、各産業の内部で起きていることを明らかにする。この産業内の生産性上昇に深く関係しているのが、90年代後半から進展したICT(情報通信技術)革命だ。ICTを生産する産業(電機、郵便・通信)では高い生産性上昇を実現した。しかし、それ以外の製造業や流通業(商業・運輸業)などICTを投入する産業では、その投資が行われなかったため、生産性上昇が大きく停滞している。米国がICT生産産業だけでなく、ICT投入産業でも、生産性上昇が加速し、ICT革命が起きたのと大きく異なると指摘する。
生産性上昇の格差は、産業別だけでなく、大企業と中小企業の間にもみられる。実は大企業の生産性上昇は堅調で、停滞したのは、1990年から95年の時期に過ぎない。大企業にとっては、たかだか「失われた5年」であることをデータ分析から発見している。これに対し、中小企業は、研究開発投資や対外直接投資も思うようにできず、アジアとの分業体制も築けていない。系列が壊れ、大企業との取引関係が希薄になり、技術の拡散効果も減速している。
しかし、大企業で生産性が上昇したといっても、実はリストラや生産コストの削減などによるもので、製品のイノベーションにより需要を喚起するものでなかった。円高などもあり、大企業は海外移転を進め、国内で生産や雇用を拡大してこなかった。こうしたことも長期停滞と結びついている。
では、国内で生産性上昇や雇用拡大を果たしている企業はあるのか。データ分析から、社齢が若く、輸出やR&Dを活発に行っている独立系企業や外資系企業がそうだと突き止める。とくにサービス産業は多くの雇用を生み出している。
こうした分析結果を基に、著者は日本経済が長期停滞から脱出する方策を示している。ICT投入の加速によるイノベーション促進、経済の新陳代謝機能の活性化と大企業の国内回帰、対日直接投資の拡大、無形資産投資の促進である。これらの政策を発動すれば、生産性水準・イノベーションの上昇と雇用創出がともに図られ、総需要拡大と継続的成長が達成できるといい、経済効果の概算も示している。
眼前で続く経済停滞は、経済学者にとって喫緊のテーマであり、原因の解明は責務でもある。百花繚乱の感もあるが、「失われた20年」を対象にした研究はまだ多くない。著者は、政府関係の研究プロジェクトにかかわり、マクロ経済の視点と需要と供給両面から数量的に原因を分析する研究が不足していことを痛感し、本書の執筆を思い立ったという。理論と詳細なデータ分析による実証研究の成果である。
(川端久雄〈編集委員、日本記者クラブ会員〉)