[書評]
2014年7月号 237号
(2014/06/15)
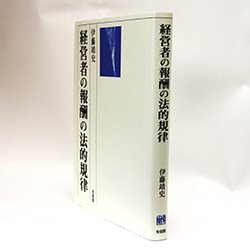 会社は経営者がいないと動かない。報酬で報いる必要がある。しかし、放っておくと、経営者は過大な報酬を手にするようになる。株主の利益を保護するため、どのような法的規律を行えばよいのか。本書はこの問題について日本の伝統的解釈論を見直し、新たな法的規律を提言する。
会社は経営者がいないと動かない。報酬で報いる必要がある。しかし、放っておくと、経営者は過大な報酬を手にするようになる。株主の利益を保護するため、どのような法的規律を行えばよいのか。本書はこの問題について日本の伝統的解釈論を見直し、新たな法的規律を提言する。
日本の会社法では取締役の報酬は定款か株主総会の決議で決まるのが原則だ。通説はこの規定を、お手盛り防止のための手続規制と解釈してきた。この解釈だと、この手続きを経ていれば、過大な報酬が支払われた、と言って株主が裁判で争うことは出来ないのだ。しかし、最近は報酬の性格が変わってきている。取締役(経営者)へのインセンティブを付与する機能を持つ点が注目され、内容も固定給の基本報酬から業績連動型報酬が増えてきている。個々の取締役の報酬額が適切に決定されているかが、株主にとっては重要になっている。報酬額が相当でない場合には、株主が報酬の返還を求める代表訴訟を裁判所に訴えられるという新しい解釈を著者は展開している。もっともこの場合、裁判所の審査基準は緩やかなものになり、株主側の主張が認められるのは、例外的なケースに限られるとしている。
従って、株主が会社法を活用する手段は限られるが、経営者の報酬を規律する手段は会社法に限らない。開示が有効な手段になる。例えば、米国では、報酬がコーポレート・ガバナンスの議論で重要な位置を占めていることもあって、企業不祥事や金融危機が起こるたびに経営者の報酬の開示が強化されてきている。新しいCEOを選任すれば、報酬内容を開示しなければならない。経営者の個人別の報酬は、毎年、会社の報酬委員会報告書の中で内訳と合計額が開示される。支配権移転に伴う支払額、退職後の報酬も含まれる。英国も個人別の報酬内容が開示されている。ドイツでも「取締役報酬の開示に関する法律」ができている。以前は、取締役会の報酬総額の開示で済んでいたが、個々の取締役の開示になった。EU加盟国もこの流れになっている。
経営者の個人別の報酬の開示は世界の潮流になっていることが分かる。
翻って日本である。実務では、報酬総額が株主総会で承認されれば、個々の取締役への配分の決定は代表取締役に一任される。会社法施行規則では、会社の事業報告で個別の報酬額を開示する方法も示されているが、義務化はされていない。個人別の報酬を知られることを嫌う感覚もあって、現実には個別の開示はほとんどされていない。このような中で、辛うじて有価証券報告書の中で、連結報酬等の額が1億円以上の役員に対して開示が行われるようになった。
こうした現実を明らかにしたうえで、日本は主要な先進国のうちで最も遅れていると、著者は指摘している。業績と報酬について株主にも判断できるように、日本も社長以下報酬額上位数名の役員について個人別の報酬を開示すべきだとする立法論を主張する。また、個人別の報酬の決定を代表取締役へ一任することを許容する多数説には問題があり、決定過程について上場規則で規律を整備することを提案している。
本書には米国の判例法理や学説が詳細に紹介されている。株式会社の機能や経営者の大切さについて理解を深められる。ディズニー株主代表訴訟も興味深い。採用した社長を、業績不振などを理由に14カ月で解雇した。退職金など総額1億4000万ドルを支払った。100億円以上である。過大支払いで、浪費だとして株主がCEOの取締役らの責任を裁判で追及した。これに対して、裁判所は、経営判断原則を適用するなどして、訴えを退けた。「(CEOは)思いもよらず、容易な解答のない状況に直面することになった。……いくつかの選択肢を衡量し、……会社にとって最善であると考える仕方で自らの経営判断を行使した」と裁判官は述べている。
米国企業がより良い経営者を得ようとして、試行錯誤をしている姿が分かる。日本企業も経営者の問題に直面している。海外M&Aの活発化でより切実な問題になっている。海外のこうした実態を知っておくのもよいだろう。
著者は大学院時代に取締役の報酬の問題に関心を持ち、15年間にわたり、このテーマの論文を書き続けてきた。通説が時代の移り変わりの中で、機能不全を起こしかけているときに、いち早くその兆しに気づき、日本の先行研究をたどり、海外を比較法的に考察し、時代にあった新しい説を展開している。学問の発展過程を見た思いがする。
(川端久雄<マール編集委員、日本記者クラブ会員>)
[Webマール]
[M&Aスクランブル]
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]