[書評]
2006年11月号 145号
(2006/10/15)
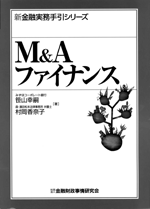
日本でもMBOやLBOが普及してきた。これを支えているのが、金融機関の買収ファイナンスである。著者らは、金融マン、弁護士としてこのマーケットの草創期から関与してきた。日本のMBOやLBOの歴史、現状、仕組みを理解するのに最適の本といえる。
買収ファイナンスとは、少ない自己資金(エクイティ)でM&Aを行うことを可能にするファイナンス(融資)である。エクイティとデット(融資部分)を組み合せ、高い投資効率を上げる点に特徴がある。20を払って、100を手に入れる仕組みとも言われる。
M&Aとファイナンスが一体化したところに最大の特徴がある。通常のコーポレートファイナンスでは、借り手が返済をする。しかし、買収ファイナンスでは、資金を借りるのは買い手側だが、返済するのは、買収された対象会社となる。買収側のリスクはエクイティ部分に限定されており(ノンリコース)、対象企業のキャッシュフローが重視される。借り手と返済人を一致させるため特別目的会社(SPC)や対象会社との合併が利用される。
こういったファイナンス面や、M&Aの手続き面が、わかりやすく説明されていて、買収ファイナンスの特徴がよく理解できる。
どうして、こういうファイナンスが必要になったのか。元来、M&Aは、自社株を対価に使えばできた。しかし、買い手が上場企業でないと、自社株は使えない。それで、ファンドなどが行う企業買収には、買収ファイナンスが欠かせないものになったという。
米国で、1980年代に隆盛を極めたが、日本では、98年に第1号が生まれたばかりである。その後の発展は目覚しい。ファンドが仕掛けるMBOが中心だったが、最近では、ワールドのような事業会社の経営陣が行う大掛かりなMBO、さらにソフトバンクによるLBOを利用した大型買収など、広がりをみせている。フィナンシャルバイヤーからM&A全体に拡大するという展望もあり、本のタイトルもM&Aファイナンスとしたのだろう。
買収ファイナンスの核にあるのは、レバレッジ(テコ)の原理の考え方である。借入金(デット)を活用して、少ないエクイティで多額のリターンを上げる。その仕組みや、借入金の担保をどう確保するのか、といった実務的な知識も得られる。
すでに日本でもLBOの時代が到来したという見方もあるが、敵対的買収の手段に使われる可能性はどうか。著者らは、現時点では法的に難しいという。買収側が買収資金を調達するためには、対象会社が担保を提供しなければならず、そのためには、取締役会決議が必要になるからだ。取締役会が同意し、100%支配が可能になる友好的買収のケースでないと、LBOの利用は難しいという。
M&Aの本もたくさん出ているが、概説書でなく、こうした専門分野の解説書が求められる時代に日本もなったのだと思う。(青)